
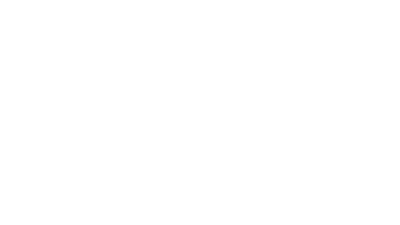
首が長いカイツブリ。冬鳥として九州以北の河川、河口、湖沼、海上に渡来する。
琵琶湖では越夏個体やヒナが記録されている。
京都府内では桂川、三川合流、阿蘇海、若狭湾などで観察され、桂川では越夏個体も確認されている。
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 確率 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
バードウォッチングのルーツ
本種の名前の由来である冠や首の夏羽は美しく、19世紀のイギリスでは女性のファッションに多用されました。そのためにカンムリカイツブリが乱獲され、一時は絶滅しそうになりました。
それを防ぐべく、1889年に創立されたのが「王立鳥類保護協会」((RSPB=Royal Society for Protection of Birds)。
この団体が、野鳥を捕獲したり飼育するのではなく、自然のままの姿を見て楽しもうという運動を始めたのがバードウォッチングのルーツだそうです。Bird Watchingという言葉が生まれたのも1901年。 鳥を観察するという楽しみを生み出したのは、カンムリカイツブリだったわけです。
アメリカの野鳥保護団体「オーデュボン協会」も、女性のファッション用にダイサギが乱獲されるのを防ぐために誕生しましたから、経緯はよく似ています(ダイサギのページ参照)。
ちなみにオーデュボン協会の会員数は56万人。一方、英国王立鳥類保護協会の会員数は何と300万人、世界最大の野鳥保護団体です。